日本人がピアノと仲良くなるために遺しておきたい言の葉
[第1章] 楽器の機能的奏法について
遺言その1 ハンマーは本当に、弦に当たっているか
からかわれているように思えるかも知れないが、百聞は一見に如かず。
ご自分でピアノの中を覗き込みながら鍵盤を下げ、確かめて見られると良い。
グランドであれアップライトであれ、どちらのタイプでも、羊毛を固めて出来たフェルト製のハンマーが、いわゆる弦と呼ばれる鋼鉄線に近づいて…「あれっ?当たってない」と殆んどの生徒さんが驚かれる。
もちろん当たらなければ、音の出る訳がない。
実際は根元を押し動かされたハンマーが途中、ある時点からは余った勢い、つまり惰性で弦に、一説では音速より速く、瞬間的に当たっているため目には見えないのである。
まさに“百聞は”の結果、見えない事を悟るわけ。
バイオリン属が弓で擦奏するのに対して、なぜピアノは弦に一瞬だけハンマーを当てて、触れ続けないようにするのか?
要するに振動を止めてしまうからで、この事をすなわち“打つ”と言う。
他の打楽器、たとえば太鼓など、持ったバチを張られた皮に打ち付け、
いちいち止めていたら音が鳴らなくなる事ぐらいは子供でも気がつく。
複雑な機構を持つピアノではあるが、鍵盤を下げただけで打弦がかなうからこそ、老若男女を問わず、誰でもが容易に音を出せるのである。
また鍵盤を下げた後、どう力を加えても、音は絶対に変化しない。究極、弦を打ったあと、どうやって即座に力を抜くかも楽器の構造上 、最大のポイントとなる。
ちなみに張られた弦をはじいて音を出すチェンバロは鍵盤つきの撥弦楽器、オルガンなら同じく鍵盤つきの管楽器と呼べる。
なおクラヴィコードなる鍵盤楽器も、バッハやヘンデルが活躍した時代までは愛奏されていた。
鍵盤を下げると、向こう側が持ち上がり、タンジェントと呼ばれる金属片が弦を押し上げて音を鳴らす、なんともシンプルな仕組み。
鍵盤を押したあとも上下に細かく動かす事によって、いわゆるビブラート、音が揺れて聞こえるような表現すら可能な、単純ゆえに成せる技を備えているのだが、惜しむらくは音量が少ないこと。
ただ序章でも触れたピアノの騒音問題の立場から考えて見ても、仮に「うるさい」と思えば、防音して蚊の羽音ぐらいにしか聞こえなくなっても、却って気になるもの。
耳をそばだててしまうからであり、逆を言えばクラヴィコードの音でも、好意と興味を持って聞けば、音像がはっきりと見えてくる。
ピアノも音量だけが総てでない事は、有効であるからこそ、なお心しておくべきである。

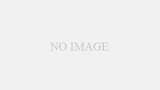
コメント