日本人がピアノと仲良くなるために遺しておきたい言の葉
[序章] あるピアニストの述懐
前回:②ある作曲家は、こう弾かれるべきである、はこちらから
③まずは楽しく弾くのが第一であり、又こうすれば、すぐに弾けるようになる方法がある
こんな事が言えれば本当に幸せなのだが、残念ながら理想論でしかない。
わが子が発表会で一生懸命にピアノを弾く姿を見れば、
親としては嬉しいかも知れないが、弾いている本人は真剣そのものであり、楽しさを感じる余裕などないはず。
親だって楽しい訳ではない。微笑ましいのである。
ただ中には「人前で弾くのが楽しくて楽しくて」
と言われるお子さんもいる。
まさに天賦の才である。大いに認めて上げてほしい。
それでも「大人になるにつれ、そうとばかりも言ってられなくなったけどね」と漏らされる御仁も、けっこう居られるが。
いっぽう「うちの子は趣味でピアノを弾いているんですから程々に」と考える向きも。
ではスカイダイビングを趣味にしている方に、
いい加減な指導をするであろうか?
音大の受験生ならいざ知らず、適当な教えかたをされて深刻に悩むのは、
腱鞘炎などで手を痛めた時ぐらいと言う嘆かわしい現実は、
多くの苦言が呈されるのを待つまでもなく、
鍵盤を押せば曲がりなりにも音が出てしまう楽器の特性に原因があるのは否めない。
一般の見方と判断するのは早計に過ぎるとしても、
ある日、面白半分にインターネットで<ピアノ>と入れて検索を掛けて見たら、
最初にヒットしたのが騒音問題と言うのは、決して笑えぬ話。
だいぶ以前ではあるが、ピアノを練習していた子供と、
その親を、同じ団地の上に住んでいた男が刺し殺してしまうと言う、
本当に痛ましい出来事があった。
これとて<ピアノ殺人>と言う事件はあっても、
<バイオリン殺人>は起こり得ない気がする。
『サザエさん』でもマスオさんの弾く腕前がネタにされてしまうぐらい、ヴァイオリンをある程度、弾けるようになるのが容易でないのは誰もが知っている。
そこまで分かっていれば、逆に気にもならぬものである。
ところがピアノとなると、出している音の高さは合っているのに、
何か違う。
練習したくないのに、いやいや弾かされているのも実は良く伝わってしまうし、
ましてや母親が傍らで手を叩きながら拍子を取っているのが聞こえるなんて言うのも、そうとう神経を逆撫でするものらしい。
そのうえ夜勤あけだったとか、ノイローゼ状態だったとか、
勝手に想像を働かせて犯人を弁護する気など微塵もないが、
他人に殺意を起こさせるほどの無神経な音も容易に出せる楽器が
ピアノだと言う事実は、認識しておくべきである。
もちろん上手く弾いていれば、それで良いわけでもないし、
上手く弾いているなどと言う思い込みこそ、
マスオさんのヴァイオリンより厄介な実情を孕んでいる。
騒音問題は、あまりにも極端な例なので、さておき、
ピアノの本当に美しい音を何割程度の人が出せているかと言うと、
かなり怪しい状況と言わざるを得ない。
考え方を換えると、
美しい音なんてピアノに求めていない場合すら多くある。
たとえば音大では、ピアノを専攻している以外の総ての学生に、
副科ピアノが必修とされている。
どうしてか?
私が思うに、いちばん顕著な理由は、弦楽器や管打楽器の人たちが普段、
眺めている楽譜にある。
楽器を操るのに両手がふさがっている都合上、
楽譜をめくる回数を減らすため、彼らは自分のパート譜しか見ていない。
全楽器の譜面が記された“スコア”と呼ばれる総譜を見ているのは、
オーケストラなら指揮者、室内楽ならピアニストのみなのである。
やはり両手を使うピアニストだけ、譜めくりの手伝いを頼む場合もある。
要するに、指揮者とピアニスト以外の楽器奏者は、
たとえばバッハが書いた無伴奏のための作品など、
何か特別な指定のある以外は、原則として常に、
ある楽曲の一部しか弾いていない。
だからこそパートではなく、一人で全てを受け持ち、
音楽をまとめてみる必要もあるため、
いちばん身近な鍵盤楽器と言えるピアノを弾かせるワケ。
ちなみに声楽科の学生は総譜を眺めているのだが、
音楽を自分一人で仕上げると言う課程で、ピアノを学ぶ事情は同じ。
一度に把握する量が十段以上に及ぶことなど、
ざらにある指揮者の眺めるスコアに比べれば、
たった二段に集約されているピアノの楽譜は、はるかに理解しやすい。
“のほほん”と当然のごとく総譜を眺めている我々ピアニストに比べ、
自分のパートしか見ていない他の楽器奏者の方が、
普段よほど神経を研ぎ澄まして回りの音に耳を傾けているのも確かなのだが、そんな彼らでも、
ただ義務感に駆られてピアノへ向かわされているだけだとしたら、
楽しく弾いている訳がないし、
ましてや美しい音なんて求めるだけ野暮と言うもの。
学ぶ目的が違うからなのだが、
ところで
「そう言えば、“あらゆる作曲家は楽しく弾かれるべきである”と豪語していたではないか」
と喰ってかかりたくなった、ご同輩。
よく文章を読んで頂きたい。
私は、“まず楽しく”と言う考え方で指導を始めるのを諫めているのである。
ピアノの弟子でありながら、友人とも呼べる同年代の女性より
「それだけピアノが自在に弾ければ、もう楽しくて仕様がないでしょう」
と感心された覚えがある。
あながち否定する気もなくはないが、弾けるだけでは、
まだ不充分と言う理由を、また他の章の中で述べてみたいし、
いっぽう向学心を持ち続けるのが人間としての業と言うもの。
まさに“上を見ても下を見てもキリがない”のを重々承知しながら、
飽くなき研鑽と発見の日々であり、
本当の楽しさは、そこにあるのかも知れない。
もう一人、別の愛弟子から聞いたピカソの話も紹介する。
ある時、カフェで友人から「似顔絵を描いて欲しい」と頼まれたピカソは、紙で出来たコースターの裏に筆を走らせた
やがて書き上げた似顔絵を渡すとき、
「はい100万円」との貨幣単位ではなかっただろうが、
要するに相当な高額を要求したのだそう。
驚く友人に「君は今、僕がこの絵を5分で描いたと思ったかも知れないけど、本当は描けるようになるまで50年も掛かっているんだ」
と伝えたのだとか。
私も、あと5年ほどで当時の彼が掛かったのと同じ年数、
ピアノを弾いている事になるのだが、
なるほど「少なくとも“すぐにピアノが弾けるようになる”と言う謳い文句だけは疑わしい」
と敢えて指摘しても、ピカソなら怒るまい。
誤解のないよう申し添えるが、レッスンを厳しくするべきだと勧めているのでは決してない。
ぜんぜん練習をして来ないのは困り者だが、
真面目に取り組む生徒に対して先生が怒るのは、
明らかに自分の教え方が不適切なのにイライラしているだけである。
本来、演奏中に過度の緊張は禁物である。
ただ私の師匠は恐ろしい人で、レッスン中に
「なんで、そんなに体を固くしているのっ」
と良く指摘されたのも解らなくはないが、
これって町で運悪く出会った、恐いお兄さんに
「ほら、ちっとも恐ろしくなんかないでしょう。もっと笑ってみせてよ」
と絡まれているのと似てません?
なんて言ったら怒られるだろうなあ、そりゃ今でも絶対。
自分のレッスンはと言えば、突然キャンセルされた、
お弟子さんから次の週に
「すみません。この間は花火大会を見に行ってしまって」と言われた際、「ええっ。それはひどい。どうして誘ってくれなかったの?」
となじったら「そうでしたね」と謝られた事はあるけど。
こんな覚えも。
ある女性のお弟子さんをレッスンしている際、
彼女が弾いているのを聞きつつ、何の気なしに笑ってしまったら、
後で「どうして笑うんですか」と文句を言われた。
これは失礼だったと反省し、
「うーん、じゃあ怒りましょうか?」と尋ねたところ、
しばらく黙って考えられた末、ぽつりと
「笑ってください」
と言われたのには思わず、いっしょに二人で笑ってしまった。
ちなみに私が自分のメソッドにキャッチフレーズを冠するとすれば、
“のんびり、きちんと”。
根気づよさと誠実さをモットーにしている。

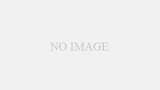
コメント