
「紅葉」のレッスンを受けました!
まずは発声練習から!
発声:声から出さず、息から出す。
前田の場合、息が止まっていて、前に飛ばない。
先生に前田の発声をマネしてもらうと、
声が窮屈に縮こまっている感じでのびやかでない。
まず、喉を開けておいてから出すこと!
発声音階練習「Ya Ya Ya Ya Ya」
音階練習の際、ひとフレーズ終わるごとに、
「休め」のよう身体を戻してはいけない。
身体の状態はそのままで、次の発声にあらかじめ備えておく。
つまり、
・支えをキープしておくこと
・腰を入れておく
・軸を崩さない
武道で言えば、相手と対峙している時に戦闘態勢は崩さない、
一瞬でもスキをつくらない、というのと同じであろう。
高音を出すコツ
高音を出す際、なにか「ひっかかって」声が出たら、
つまりスムーズに声が出なかったら、
口の中を開けるとき、漏斗をさかさまにしたように、
尖がって開けるイメージでする。
注意点として、口の上をあけると声が出ていく矢印が上になりがちである。
すると声は前に飛ばない。
なので、口の中を上に開ける上向き矢印と、
声を前に飛ばす前向き矢印、これら二つを意識する。
そのうえで、よい声を出す、ちょうど良い位置=ポジションを探し当て、
いつでも百発百中、ブレないようにトレーニングを重ねるのだ!
楽器の音の上に声を乗せる
前田が発声練習や歌を歌っている時よく注意されるのが、
「横に開いて」歌っている、ということだ。
それでは口の中が潰れてしまい、響きのある声は出ないし
その響きが落ちてくるという。
すると楽器の音の中に声が埋もれてしまうのだ。
発声がきちんとできていれば響きが落ちてこないので、
楽器の音の上に乗る。
つまり歌がきちんと聴き手に届くのだ。
また、おなかをきちんと使い切らないといい声は出ない。
先生たちは、きちんと身体を使っている声と
そうでない声はちゃんとわかるという。
紅葉を歌ってみた
秋の夕日に 照る山紅葉
濃いも薄いも 数ある中に
松をいろどる 楓や蔦ハ
山のふもとの 裾模様
渓の流れに 散り浮く紅葉
波にゆられて 離れて寄って
赤や黄色の 色さまざまに
水の上にも 織る錦
明治44年六月尋常小学唱歌第2学年用
高野 辰之 作詞
岡野 貞一 作曲
※向かって一番左が、あんぷらぐどでもコンサートをしていただいている、
フォレスタ・内海万里子さんだと思うのですけど。。。
歌詞を読む
前田はプロのアナウンサーの朗読を聞いたことがある。
アンデルセン童話の朗読なのだが、
本当に情景が浮かび、気持を感じるような、
ストーリー・物語に惹きつけられるのだ。
が、読んでいただくとわかるが、かなり難しい。
我々素人が読むと、小中学生の読み方というか、
「ただ読むだけ」になりがちである。
歌詞を音読するのは「上手に歌うために読む」。
どういうことであろうか??
イントネーション、単語の読み分け、気持ちの入れ方、、、
これらができると、言葉がクリアになる。
読み方に起承転結があり、語尾も落ちない、音色も落ちない、
これがすらすらできると、歌ってもきれいに歌えるのだ。
前田の場合、ひとフレーズの読み終わり、
つまり語尾を落としておさめてしまう。
実はこの、「読み終り = 歌い終わり」なので、
語尾が落ちてしまっては、
歌が聴こえないし、「聴き心地の悪い」歌い方になる。
きちんと語尾の終わりを「開けて落とさず」が大切だ。
紅葉を歌うコツ
曲を選ぶとき・歌う時は、
歌をどういうふうに最後まで持っていくか=歌うか
を考えることが必要になる。
四拍子四拍だが 二拍子二拍と思って歌うとよい。

◇秋の夕日に 照る山 紅葉
秋の「あ」:
前田が歌うと、「(ハ)あ~」のように、
「あ」が母音でピタッとはまらない。
先生曰く「ゆるい」。お腹をきちんと絞めていないのだ。
また、F(フォルテ)に聴こえるという。
緩くてフォルテ??なのだが(笑)、
歌う前のおなかの緩みは、太い声を太い息で出してしまうため、
すかすかに聴こえるのだ。
楽譜の指示はmp(メゾピアノ)。
mp(メゾピアノ)で歌う「息づかい」がある。
これは今後の宿題である。
夕日にの「に」:
ここは音程が低いため、一緒に声まで落としてしまう。
なので、それを落とさないために、上げるために、
通常より何倍もお腹を絞めて歌う。
裾模様の「す」:
「う(U)」は「ウッ~」と前に出さない。
口の中で鳴らすように、息をなるたけ外に出さない。
裾模様の「う(お)」:
す~そぉもよお~ と発語するので、よ(yo)の「o(お)」のまま、
yo-o(よぉ~お)と喉で切り変えずそのまま歌う。
歌の歌詞を母音で歌って、それに歌詞を当てはめ、
自分のいちばんよくなるところでつなげて歌う。
これができればきれいな日本語に聞こえる。
発声のまとめ
前田がよく言われるのが、
何気なく歌いはじめたり、歌っていてはだめ。
きちんと準備してから歌い出すこと。
準備して、一番良く鳴るところに母音が来ていないと、歌が崩れる。
音域によって違う音色の声が違ったり、
高音部で出るはずなのに、低くなってしまう・音がはまらない、
といったことが起こる。
人と日常会話を話している時でも、実はおなかをきちんと使っている。
おなかが緩むことはないのだ。
なので歌う時に、しゃべり声よりおなかは緩むことはない。
が、歌うとなぜかゆるゆるで歌ってしまう。。。
このように、おなかのコントロールが非常に重要になる。
「一番効率よく一番きちっとした、
ぴたっと響くところで声を出す」
これがいついかなる時でもブレないように、
練習とレッスンを重ねていこう!
「‘音楽’時間」で演奏する!
語尾のあとに、心地よい空白・間がきちんとある。
聴いているほうが、心地よさ・余韻を感じることができる、
間や空白が大切になる。
歌う場という空間、自分(歌い手)、お客様―
そのような空間を活かした歌い方、間の取り方、話し方があるのだ!
歌の先生はこれを
「‘音楽’時間」と称した。
日常の生活で感じる時間とは違う「音楽時間」。
数秒という、ほんのちょっとのわずかな時間で
至福の時間を味わえる―
なんと素晴らしいことでしょう!
さあ、更なる高み、レベルアップを目指して、
レッスンを楽しみませんか!
【楽譜はこちら】
ちいさい秋みつけた~虫のこえ~里の秋~赤とんぼ~紅葉(もみじ)


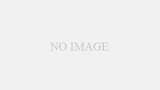
コメント