日本人がピアノと仲良くなるために遺しておきたい言の葉
[第1章] 楽器の機能的奏法について
遺言その11
アウフタクトを切らない場合も、なお手首を浮かせながら弾く
前の遺言でも触れた、1拍目を弱く弾くのが、
今度は切らず、レガートで滑らかに結ばれる場合の顕著な例として、
メンデルスゾーンの『厳格なる変奏曲 作品54』を取り上げる。
四分の二拍子で書かれた主題は2拍目より始まるが、
音楽的なエネルギーは寧ろ、この拍に掛かっており、
“緩急法”と解される<アゴーギク>を意識するなら、
個人差はあるものの<テヌート>で“たっぷりと”長めに弾くべき。
肝心なのは音を切りこそしないものの、
手首を上に引き上げるようにしながら弾くこと。
都合、2拍目の裏に当たる左手のドと右手のミも
手首は浮いたままで鍵盤を押し、次の1拍目で着地するように、
手首は降ろすが強くは弾かない。
拍の感じ方を簡単に明かしてしまうなら
「にーいーとーおーいちとお、
にーいーとーおーいちとお」と言った雰囲気。
この感じ方を3回繰り返しつつ、
音の高さが徐々に上がっていくため
2小節目の2拍目で頂点を迎え、
3小節目は言うならば手綱をゆるめ、
下へ向かって音楽を前へと進める。
4小節目の、<ドミナント>に当たる1拍目の和音は強めに、
やや長く伸ばしてフレーズー楽句ーをまとめ、
2拍目から同じ要領で、次のフレーズを歌う。
8小節目の1拍目は、和音がへ長調の<トニック>に当たるので、
弱く収める。
いちおう“遺言”と謳っている以上、包み隠さず申し上げるが、
当変奏曲の主題で、いま詳述した前半8小節の部分をどう弾くべきか、
永年に亘り、悩み続けていた。
最初に舞台で弾いたのが高校生の時。
再演したのが、つい最近なので30年近く拘り続け、
プログラムへ載せるのを封印していた勘定になる訳。
もちろん各変奏曲によっては、捉えやすいものもあるいっぽう、
新たに考え直す必要が生じる場合もあり、
ピアニストの諸氏からは嗤われてしまうのかも知れないが、
曲が本当に理解できているかどうかは、あくまでも個人的な問題であり、
敢えて吐露してみた次第。
実は、四拍子ではあるものの、
二拍子が倍にひきのばされたものとして、
この変奏曲と同じ捉え方をするべきなのが、
ベートーヴェンの、ハ長調で書かれた『ロンド 作品51-1』。
偶然とは言え『厳格なる変奏曲』と同じく、
当ロンドも第8小節の3拍目からは理解できるものの、
そこまでが分からず、大学院時代に受けていたクラス講義で、
この作品を取り上げた際、教授に質問してみた覚えがある。
残念ながら、あまり芳しい答えは得られず、
まわりにいたクラスの仲間も自分が何を悩んでいるのか、
要するに「曲の出だしが3拍目からではなく、
1拍目から始まっているようにしか感じられない」
と言う訴えを理解できないようだった。
ただ、この楽曲も拍感について納得した上で最近、
ステージで弾いてみたところ、思いのほか好評だったことから察すると、
曲がりなりにも熟考を重ねた成果が顕わたのかも知れない。
ブゾーニや、ブラームスにいたっては左手のための練習曲として、
各々アレンジしている、
バッハが無伴奏ヴァイオリンのために書かれた名作『シャコンヌ』は、
さらに興味深く、原曲に、より近いブラームス版を参考にする。
四分の三拍子で2拍目より始まるが、
ここでも手首を引き上げるようにして鳴らされたレファラの和音が
<タイ>によって3拍目では伸びたまま、
裏の八分音符によるレファラまで緊張が保たれる。
やはり第1小節の1拍目で手首が下がるが音は弱く、
2拍目ではバスのド♯のみ<遺言その7>で紹介した、
斜め下の奥の方へ放る感じで鍵盤を下げたあと、
手首を上げながらソラミの和音を弾く。
拍の感じ方を言うなら
「うんったーあたたんっ、たーあたたんっ」と言った具合。
これが3回つづいてから、第3小節の2拍目は軽く流し、
3拍目は<ドミナント>なので手首を浮かしながら強く、
第4小節1拍目は<トニック>のため、手首を下げつつ弱く弾く。
続く2拍目から同じパターンが繰り返されるが、
第6小節3拍目裏のレは、敢えて手首を下げて弾き、
7小節目の上声部で奏されるシ♭ラソファソミは、
メロデイのクライマックスではあるものの、
すべて手首を上げながら奏する。
第8小節の1拍目、ファラファの和音は、
主題を締めくくりつつ、副旋律がレの音より同時に弾き出され、
第一変奏へ入っていくと言う、はなはだ凝った作りになっている訳で、
左手のみは言わずもがな、
ヴァイオリン1本で演奏させるバッハのアイディアも相当だなと思う。
以上、三つの例を上げてみたが、言うまでもなく手首の上げ下げが、
効果的かつ必要な箇所は曲の中で、それこそ無限にある。
裏拍を演奏するのに手首をどう使うかの原理は、
機能的奏法によるものの、ただ単に
「楽器をどう鳴らすか」と言う問題に留まらず、
音楽的な捉え方にも大きく影響を与える、
きわめて大切な要因であるのは間違いない。
今日もお読みいただきありがとうございます!
あんぷらぐどピアノ講師は、男性2人です。
一人は現役ピアニスト・言の葉T先生。
もうひとりが、その愛弟子O先生。
この、年間多くの本番をこなす、ソロも伴奏もおまかせ!な
現役ピアニストが熱心に丁寧に教えてくださいます^^
まずは体験レッスンにお申し込みください♪
T先生・・・おもに土曜日に1回~から 日時は応相談
http://www.salonde-unplugged.jp/piano-ka.html
こちら 埼玉県春日部市のピアノ教室:ピアノ講師・プロ育成!【学び屋あんぷらぐど】ピアノ講師・プロ育成コース|ピアノセミナー|上級者向け
O先生・・・毎週金曜日:こども年42回プラス2回補講
大人月2回、月3回~
★O先生のレッスンはこちら♪
・こどもぴあの⇒ http://www.salonde-unplugged.jp/kids-piano.html
・大人のピアノ⇒ http://www.salonde-unplugged.jp/pianotaiken-miyosi.html
・保育士⇒ http://www.salonde-unplugged.jp/hoikusi.html
★ほか、月1回の演奏会あり♪
http://www.salonde-unplugged.jp/unplugged-cup.html
春日部豊春の実力派ピアノ教室:学び屋あんぷらぐど
048-755-2363
電話受付:10時~20時 火曜日定休

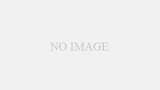
コメント