歌心を世界の大空へ響かせるぬしこと前田です。
赤とんぼを歌いました。
季節外れですけど(笑)
赤とんぼ 山田耕筰作曲
山田耕筰といえば、名前と曲を、少しく知っているというほどでした。
あ、これも山田耕筰なのね、ということもしばしば。
今回「赤とんぼ」を実際歌ってみて、
ま、いつものようにウイキペディアですけど(笑)、山田耕筰を知ると―
山田耕筰って結構波乱に満ちた人生を生きてこられたのですね~
写真を見ると、音楽家というのか、目チカラのあるおっさんやなあ、
というのが正直な感想ですw
あんぷらぐどボイトレの先生曰く、大意
「ドイツで学んで、ブラームスなどの薫陶を受けて
日本でその音楽を広めようとした。
なので赤とんぼもそうだけど、ブラームスっぽい曲が多い」
へ~~、と思いながら聞いていたのですが、
・・・ブラームスってどんな曲だっけ???(笑)
無知なマエダです。。。
※この曲の前半は、シューマンの
『序奏と協奏的アレグロ ニ短調 op.134』
(Concert – Allegro with Introduction for Pianoforte and Orchestra Op. 134)
の中で18回繰り返されるフレーズに酷似していることが指摘されている
引用:ウイキペディア

歌唱のコツ
夕焼小焼の 赤とんぼ
負われて見たのは いつの日か
山の畑の 桑の実を
小籠に摘んだは まぼろしか
十五でねえやは 嫁に行き
お里のたよりも 絶えはてた
夕焼小焼の 赤とんぼ
とまっているよ 竿の先
で、、、
何も指導される前に歌ってみると、、、!!
・・・息が続かない!!
「負われて見たのは」の小節がダメだった。
え、そんなに長くないのに。。。
ここは一息で歌いたいところ。
しかし途中で使いきってしまいました。
この部分はフォルテで歌うので強く歌ったのですが、、、
先生曰く
「フォルテは下から突き上げると続きません。
先を見通して歌わないとダメ。
このフレーズは一息で歌う!と決めて歌うのです!」
「負われて見たのは いつの日か」
レガートに歌うには、お腹に力を入れて歌わなければならない、
を実感した前田です^^
「やあま~のはたけえ」で
前田が歌うと、「や」から「ま」を、
下からしゃくりあげているように聴こえます。
音が潰れて聴こえる。
音は丸い粒のように、と教えてもらっいましたが、
その粒が潰れて出てきたような感じです。。。
いやあ、歌いこなすにはかなり大変です!!
発音のコツ~舞台語として
いろいろと歌詞の発音について学びました。
観客に聴きやすい発音、という意味でしょうか、
先生は舞台語といっています。
・「いつの日か」
ひ(日)を hi ではなく shi のように
「し」に近い発音をするといいらしい。
・「桑の身」 こわのみに近く。
・「まぼろしか」 shi を意識する。やりすぎると江戸っ子にwww
最後に
この曲は歌いこなせれば、
気持ちよいですね。
リズムと発声・歌詞・発音―
こういう皆が知っている曲は、プロでも気が抜けないとか。
やはり実力が問われますね
前田自身の発声については、
細い声が太くなり声量がついたとか!
うれしい^^
が、、、
軸がぶれる、とか。
なので、声が出るポジションがいちいちずれる・ブレる。
声を届かせる的(まと)が一定しないのですね。
あと、ひとフレーズ歌うと、身体もリセットされてしまう。
つまり、ひとフレーズ歌い終わって
せっかく歌うための身体になっているのに、
歌い終わるとその歌う身体が元に戻ってしまい、
また準備し直さなければならない。
歌った、力抜いて休んで、さあ準備して―
みたいに、いちいち無駄な動きになっているので、
なかなか発声が安定しない、ということです。
う~ん、課題です。
参考
「作詞:三木 露風
(みき ろふう、1889年(明治22年)6月23日 – 1964年(昭和39年)12月29日)
日本の詩人、童謡作家、歌人、随筆家。本名は三木 操(みき みさお)。
近代日本を代表する詩人・作詞家として、
北原白秋と並び「白露時代」と称された。
若き日は日本における象徴派詩人でもあった」
引用:ウイキペディア

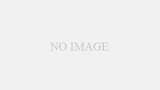
コメント