あんぷらぐど受講生がよくレッスンで歌う『宵待草』。
今回はそのうんちくを調べました。
で、新たに知ったことがたくさん。
いやあ、全く持って無知ですね(笑)。
「宵待草」
待てど暮らせど来ぬ人を 宵待草のやるせなさ 今宵は月も出ぬさうな
まず竹久夢二の作詞だということ。
・・・といっても竹久夢二について詳しい訳ではありませんが^^
さらに調べていって知ったのが、、、
最初のレコードは昭和3年、日本ビクター蓄音機から出され、
その歌い手・藤原義江が、藤原歌劇団の創設者だということ。
藤原義江については全く知りませんでしたが、
藤原歌劇団にはなじみがあるので、
今回、へ~~~、と思った次第^^
で、実は一番興味を持ったのが、作曲者。
こういうメロディをこの詞に付けた人はどんな人なのだろう? と。
「多」さん? た・さん?? 何て読むのだ??(笑)
調べてみると、
「多 忠亮(おおの ただすけ、1895年(明治28年)5月3日
– 1929年(昭和4年)12月3日)は、
大正期のヴァイオリン奏者・作曲家。
東京生まれ。旧制芝中学校(第8回生)を卒業し、
東京音楽学校(現・東京藝術大学音楽学部)入学。
宮内省式部職楽部所属の雅楽の家柄の出ではあるが、
彼自身は洋楽に専心し、ヴァイオリンを専攻する。
竹久夢二の「宵待草」の詩に感動、
これに曲を付けて1918年(大正7年)セノオ楽譜より出版、
またたく間に日本中の心をつかみ一世を風靡した。
多(おおの)家は、
古事記を編纂した太安万侶(多安万呂:おおの やすまろ)の子孫の家系とされ、
先祖には平安期に伝統神楽の形式を定めた多自然麿を擁しており、
代々皇室に仕える楽人家として多くの雅楽家を輩出した。」
引用:ウィキペディア
なるほど~~。
何かなぜか、妙~に納得です^^
国民的愛唱歌に
その後、昭和17年の李香蘭盤まで、
戦前だけで15年間に少なくとも18枚のレコードが出されているそうな。
いろいろな人が歌っているのですね~~
それもそのはず、
「『宵待草』(宵待ち草:よいまちぐさ)は、
大正浪漫を代表する画家・詩人である竹久夢二によって創られた詩歌。
バイオリン奏者・多 忠亮(おおの ただすけ)が曲をつけ、
1917年(大正6年)5月12日、
第2回「芸術座音楽会」(牛込藝術倶楽部)で初公演された。
翌18年に「セノオ楽譜」(セノオ音楽出版社刊)
の一編として夢二の表紙画で出版され、
たちまち日本中に広がり多くの人の心を捉えて口ずさまれ、
後々まで歌いつがれる不朽の名作となった。」
引用:ウィキペディア
「夢二の表紙画で出版され、
たちまち日本中に広がり多くの人の心を捉えて口ずさまれ」た。
とにかく流行ったのでしょうね(笑)
こんなにたくさん歌う人がいるとは、
国民的愛唱歌といえますね。
恋多き夢二であったそうなので、
「実ることなく終わったひと夏の恋」
に、当時の国民は一篇の映画を見るような切ない甘美さをもって
この曲を愛したのでしょうか。。。
2番があった??
んん??
あんぷらぐど声楽レッスンで使っている楽譜の1番の下に、
何やら手書きの歌詞があるぞよ^^
調べていくと、2番があった!
「夢二が亡くなって4年後の1938年に、
その爆発的人気にあやかり『宵待草』という映画が企画された。
その際、映画の主題歌にはこの3行の歌詞は短すぎるとして、
夢二と親しかった西條八十によって新たに第2番の歌詞が加えられた。
(略)
第2番が歌われることはほとんどなかった」
引用:ウィキペディア
待てど暮らせど来ぬ人を
宵待草のやるせなさ
今宵は月も出ぬさうな
暮れて河原に星一つ
宵待草の花のつゆ
更けては風も泣くさうな
第2番が歌われることはほとんどなかった・・・って(笑)
歌ってみよう・聴いてみよう
「♪ま~て~どくらせど」
「ま」から「て」までいきなり8度(?)も上がる!
素人には歌えんぞ!ww
呼吸や身体の内部でどれだけの準備を
「ま」から「て」の1拍の中でしてるのだ、
ていうくらい大変です。
これも「さくらさくら」とか「ゆりかご」と同じで、
一音一音丁寧に歌唱できる発声力、歌唱力が必要ですね^^
♪共有ありがとうございます!!
藤原 義江 宵待ち草 蓄音機コンサート
李香蘭
高峰三枝子
参考
◆宵待草とは?
「植物学的には「マツヨイグサ(待宵草)」が正しく、
「ツキミソウ(月見草)」などと同種の、
群生して可憐な花(待宵草は黄色、月見草は白~ピンク)
をつける植物のことである。
ある時期から夢二自身が音感の美しさにこだわって
こう替えたとされる。」
引用:ウィキペディア
◆藤原 義江
(ふじわら よしえ、
1898年(明治31年)12月5日 – 1976年(昭和51年)3月22日)
日本の男性オペラ歌手、声楽家(テノール(テナー))。
愛称は吾等のテナー
戦前から戦後にかけて活躍した世界的オペラ歌手であり、
藤原歌劇団の創設者。
父親がスコットランド人で母親が日本人のハーフ。
大阪府生まれ。
レッスンのご案内
うたごえ上級クラス(月10時~)
うたごえ~楽しく歌おうクラス(水11時~)
50代~70代の方が楽しんでいますよ~~!!
無料体験レッスン受付中♪
048-755-2363

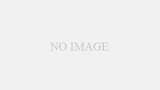
コメント