春日部豊春のピアノ教室・豊春文化会館館長こと学び屋あんぷらぐど・ぬしです^^
ピアノ講師育成および上級者を指導している冨澤裕貴先生の「遺言」です。
詳しくはこちらを御覧ください ⇒ 言の葉
[第1章] 楽器の機能的奏法について
遺言その16 その2
4から1の指をすべて使って同音連打をする場合も
<セカンドエスケープメント>を使い、“手前に引っ掻く”
試行錯誤を重ねつつ、いまだに尚、はっきりとは断定できないのが近況ながら述べてしまうと、
“手前に引っ掻く”弾き方で鍵盤の底まで押さないのも、
反応が良い楽器なら可能かも知れないし、いっぽう“つけて取り”ながら、
<セカンドエスケープメント>も使っているようにも思える。
音質が無視できないのも確かだが、
本音を言えば「弾けるかどうか」について拘るほうが現実的。
そこで機能的に加え、身体的な奏法についても少し触れていく事にして、
まずは指の取り方こそ肝心であり、
“手前に引っ掻く”より“つけて取る”弾き方に近い方が、
当然ながら運動量は少なくて済む。
第8小節目からは3-2の指で連打したあと、2-1の指に拡張を求めている。
1と他の指を開きながら弾くのは手の構造上、容易なため、
“手前に引っ掻”いても“つけて取”っても演奏は可能である。
第13小節以降も拍への収め方がずれているだけで、
アタックする音を意識すれば、弾き方は同じ。
ただし3拍目で1-4-3を使うのなら、“手前に引っ掻く”事になる。
第20小節では4-2の拡張をはさみつつ2-1の連打が続く。
4-2こそ手の構造上、開きにくいため、
“手前に引っ掻く”と手に余計な力が入ってしまう。
次章で詳述するが“つけて取る”しかない。
第16小節を注意深く眺めると、2-1が2回続いており、
この場合は“手前に引っ掻く”のでは弾きにくいと言うより、
ほとんど不可能なため、“つけて取る”方が良い。
連打について興味のある方も多いと思われるが、
以上に加え、実は1の指の弾き方を知らないと、
説明が全く片手落ちになってしまう。
たとえば第8小節の2~3拍目や第19小節など、3の指を1の上に被せる場合も、
“つけて取る”必要が生じる。
この件については次章、身体的な奏法の観点から再考してゆく。

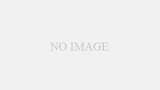
コメント